※Google日本語、Android端末などで、仕様上「一時停止」が効かない場合があります。

少年の私にとってそれはまるで要塞のような墓でした。
「たたら」で隆盛を誇り、その後大資本製鉄の波に飲み込まれるように一族は破産。
かろうじて中学だけ卒業し、紡績で地位を得た祖父は、故郷に錦を飾るごとく一族の巨大な墓を建てたのです。
高台に設置された、砲台の台座ほどもあるコンクリート製の本体の上には、村を見下ろすかのように石碑が鎮座していました。
「ほらこれがお前も入るお墓だよ。」
「ぎぃぃ、ぎぃぃーー」
お墓には開閉式の鉄門が備わり、中に入ることが出来ました。
促されるように恐る恐る中に入ってみると、空っぽのお墓には、これから数十代のお骨は収納できるであろうほどの棚だけが、整然と並んでいました。
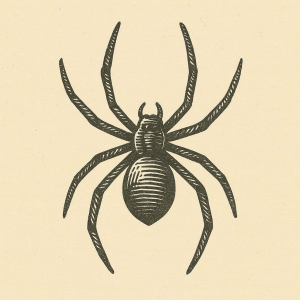
その時ふと視界の隅に、音も立てず動くものがありました。
それは巨大な蜘蛛でありました。
固い鉄門で閉ざされた中に、一体どうやって入り込んだのか。
私は不思議に思うと同時に、言いようのない不安に包まれました。
やがて祖父が亡くなり、住人を得た墓には、お参りこそ続けましたが中を覗き見ることは二度としませんでした。そしてお墓は、あのおどろおどろしい蜘蛛とともに記憶されました。
田舎の墓はとても交通の便が悪く、その後、父も多忙を極め、私も就職する頃になると、島根に行ける機会もめっきり減ってしまいました。
そしてお墓は魂抜きを行い、改めて場所を移すことになったのです。
遠方のお墓の管理や清掃を、快く引き受けてくださっていた方も、いよいよ老齢の域にさしかかっておられました。草木の勢い激しい山の中で、お墓を保つこと自体が困難になってしまったことが最大の理由でした。
そうして、いったいあの、末代まで入れるはずだった巨大なお墓は、一代にしてその使命を終えたのでした。
それでもどこか心の片隅に、祖父が残したお墓のことが引っかかっていました。魂は抜いたものの、お墓そのものは撤去することもままならず、今も高台から村を見据えているはずでした。
或る日、私は意を決して一人で島根へと向かいました。
昔の記憶を頼りに、目印となる家の裏の小道を登りました。
しかし人の手の入らなくなった山は、途中で道が消え、お墓があったはずの場所は、最早うっそうとした茂みと化していました。
祖父が一族大勢を従えて、案内してくれたころの面影は完全に消えていました。真っ昼間というのに、薄暗く、大の大人が恐怖さえ感じます。完全に方向感覚さえ失われてしまうのです。ほんの数十メートル先に在るはずのお墓は、まるで遠い遠い場所にあるかのように感じられました。注意深く目印をつけながら、歩を進めると、帰り道がわからなくなりそうなギリギリのところで墓の一部が姿を表しました。
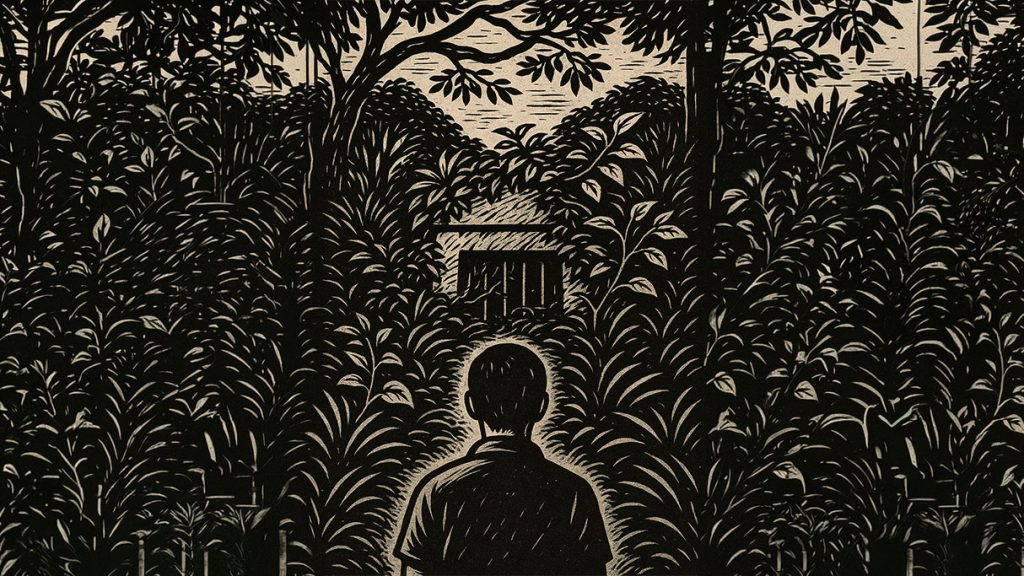
しかしそれはもう、少年の頃の記憶とはかけ離れていて、あの巨大なお墓さえも自然はすっかり飲み込んでいました。
それを見て、私は何故か安心したのでした。
帰りの車の中で、ぼんやりと考えました。
あの大きなお墓は、祖父の郷土愛であると同時に、虚栄心そのものだったのでしょう。
しかしどれだけ大きなお墓を建てても、
何も建てなくても、
そよそよと風が吹き、土を運び、草が生え、自然が包み込む。
いま祖父は、我が家の小さな和室の仏壇の位牌として、先祖や祖母たちと、ただ並んでいるのでした。



誇りは生きてきた目的であり、証だと思います。でも「永遠を残そう」としても、自然の流れにはかなわない。“消えていくこと”自体に意味があるのかも知れません。